
トップページに戻る


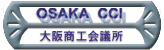
大商ニュース 平成11年1月25日号
●【G−BOC99】登録受付始まる〜海外企業と10月に商談〜 大商・大阪府・大阪市などで構成する世界ビジネス・コンベンション開催協議会は、 10月18日から20日までの3日間の日程で「1999年世界ビジネス・コンベン ション(G−BOC99)」を開催する。同事業は、海外企業と日本企業の実質的な ビジネス交流の促進を目的とした国際商談会。会期中に約六百人の海外企業関係者と、 日本企業との間で数千件にのぼる商談が活発に繰り広げられる。このほど、「個別商 談会」に参加を希望する日本企業の登録募集が始まった。 G−BOCは今年で14回を迎える国際商談・情報交換会。輸出入、合弁、技術・ 業務提携などあらゆるタイプの取引が対象で、取扱品目にも制限がないため、異業種 との取引拡大を検討中の企業や海外と取引を始めたいとする企業にも適している。 同協議会の事務局では、「どの国と、どんな分野(業種、品目)で取引したいか」 といった日本企業のビジネス・ニーズの登録内容を冊子にまとめ、海外企業・団体 (G−BOC99出展者)に配布する。一方、国内登録企業は事務局から通知する海 外の商談候補企業・団体の中から商談したい相手を選ぶだけ。事務局が仲介役となり、 個別商談の時間調整まで事前の準備を整えるので、当日G−BOCの会場に出向くだ けで希望する国の企業・団体と効率の良い商談が可能となる。 さらに、登録企業には会期中に実施する各種セミナーや専門家による貿易・投資相 談など、実際のビジネスに役立つプログラムも案内される。 登録は無料。具体的なビジネス・チャンスの第一歩として、今回の登録募集の機会 をぜひご活用いただきたい。ご関心の方は、事務局へ申込書の請求を。申込締切は2 月8日(月)。 【問合せ】大商国際部G−BOC担当・松本、伊藤TEL:6944−6404、F AX:6944−6409、Eメール=gboc@osaka.cci.or.jp
●企業売買に高い関心〜ニーズ調査から〜 大商は、このほど「M&Aに関する企業経営者のニーズ・意識調査」の結果をとり まとめた。昨年9月から10月にかけて実施、調査対象は大阪府下に本社を置く企業 の経営者で、有効回答は728社。 その結果、M&Aで買いに関心があるのは全体の約四割、一方売りに関心があるの は約3割となっている。買い関心の大部分は大企業(従業員300人以上)だが、小 企業(従業員30人未満)では売り関心が多い。売り関心の理由としては、「自社・ 業界の先行き不安」や「後継者難」を挙げている。 M&Aを行う際の不安点を聞いたところ、買い手の場合は「売り企業の情報の信頼 度」が最も多い。売り手の場合は、「売却価格の決め方」を指摘する声が多い中で、 大企業の「第三者への秘密漏洩」が目立っている。
●M&Aのメリット知って〜京・阪・神でセミナー、相談会〜 大商は2月、京都・神戸の両商工会議所とともに「M&Aプラザin関西パート (2)」を開催する。昨年10月に開催したM&Aプラザが好評だったことから、通 産省の支援を得て、2回目の開催に踏み切ったもの。 まだ広く知られていないM&A(企業の合併・買収)のメリットや実務面について、 多くの中堅・中小企業経営者に認識を深めてもらうのが目的で、京都=2月15日、 大阪=2月18日、神戸=2月23日にセミナーや相談会を開催する。 大阪では、M&Aセミナーとして、三和銀行コーポレートファイナンス部の小野啓 治氏に「経営戦略とM&A」と題し、企業の経営戦略におけるM&Aの重要性やメリ ット、実務面のポイントなどについて、ご講演いただく。 また京都、神戸ではセミナー終了後にM&A個別相談会も開催する。参加は無料。 【問合せ】経済部・上谷TEL:6944−6304
●【環境シンポ】立松和平氏が講演〜3月8日、大商ホールで〜 大商は3月8日、通産省、日商と共催で「地球環境問題シンポジウム」を大商ホー ルで開催する。 21世紀を目前にして、地球環境保全の重要性が高まり、良好な環境の維持と持続 的な経済成長の両立が求められている。そこで、資源循環型社会の必要性を広く訴え、 企業、行政、市民が一体となってどのように取り組んでいくべきかを探るのがねらい。 シンポジウムのテーマは、「環境にやさしいまちづくり」。リサイクル活動を実践 している街づくりの事例やゼロエミッションに取り組む企業事例などをもとに、行政 や一般市民も加わり、議論を繰り広げる。大阪市立大学の植田政孝教授がコーディネ ーターを務める。また作家の立松和平氏が、自然との共生をテーマに特別講演を行う。 参加費は無料。 【問合せ】産業部・原田TEL:6944−6300
●マクロミクロ 『企業行動への期待』 1998年の日本経済は、負の連鎖から抜け出せず、デフレスパイラルの危機の中 で底這いの状態が続いた。このため多くの企業は経費節減、事業所の縮小・廃止、人 員削減などリストラを余儀なくされた▼こうした当面の危機を回避しようとする企業 行動は、正当化しうるのだが、合成されるとマクロ経済の委縮・縮小を呼び、景気の 回復を遅らせてしまう。横並び意識、同等意識の強いわが国で、不況下ではいわゆる 『合成の誤謬』が不可避な恨みである▼このような中で政府は需給ギャップを埋める ため、総合・緊急の名の下に大規模な財政政策を連発してきた。ただそれらの財源の 多くは国債に依存しており、国債、借入金など政府の債務残高がすでに401兆円に 達し、後年に多大の負担を残すことになった▼ともあれ、本格的な景気回復のために は、基本的に民需の盛り上がりが不可欠である。いまグローバル化への対応と21世 紀の基盤づくりのため企業の合従連衡や技術強化が盛んに行われている。企業はいま こそ企業家精神を大いに発揮し、新技術や新製品の開発、新分野進出などにより、現 状を打破して新しい成長のを開いてほしいものだ。 (O)
●月例会員講演会<第361回>−入場無料− ◆と き 2月23日(火)午後2時〜3時30分 ◆会 場 大商7階国際会議ホール ◆テーマ 『−ノーベル賞候補が語る−最先端のガン遺伝子研究』 大阪バイオサイエンス研究所所長 花房秀三郎氏 【講師紹介】昭和4年生まれ。大阪大学理学部卒業。33年同大学微生物研究所助手、 36年カリフォルニア大学ウィルス研究所研究員、39年コレッジ・ド・フランス実 験研究室研究員、41年ニューヨーク公衆衛生研究所ガンウイルス研究部長、48年 ロックフェラー大学教授を経て、平成10年から現職。これまでに、ラスカー賞、朝 日賞、米国癌学会クルー賞などを受賞。3年文化功労者、7年に文化勲章受賞。 【問合せ】企業研修部TEL:6944−6421【定員】700人 ※申込みは不要ですが、満員の節はお断りする場合があります。また写真撮影および 講演内容の録音は全面禁止します。
●部会ご案内 ◎貿易部会 ◆日 時:2月22日 午後2時〜3時30分 ◆場 所:大商4階 401号会議室 ◆テーマ:「躍進する台湾経済と対日貿易の今後のゆくえ(仮題)」 ◆講 師:遠東貿易サービスセンター 大阪事務所長 林 盈權氏 ◆問合せ:国際部・阿部 TEL:6944−6412
●「活性化でリードを」〜大西副会頭、阿倍野支部で〜 大商では、正副会頭が分担して各支部を訪問し、地域商工業者の実情把握に努めて いる。18日、大西隆副会頭(大西衣料社長)が阿倍野支部(支部長=田中太郎・近 鉄百貨店社長)を訪れ、運営委員・振興委員らと懇談した。 出席者からは「景気の低迷で商店会は厳しい状況だが、『街づくり三法』もできた ので、自助努力で苦境に立ち向かっていかなければならない」「商店街の地域おこし イベント『あべの占い祭り』も3回目となり定着してきた。安倍晴明公没後1000 年となる2005年まで、がんばって取り組んでいきたい」「小売市場をセルフ化し、 大いに合理化できたが、食品素材の売れ行きが今ひとつ。大型店の出店が進む中で、 やめていく小売店の姿を見落とさないでほしい」などの発言が寄せられた。 これに対し、大西副会頭は「『あべの占い祭り』の盛況は喜ばしい。婦人部や青年 部のパワーも生かして、さらにもり立ててほしい。阿倍野は一大中心地なので、商業 活性化をリードしてほしい。小売市場で素材商品が売れないなら惣菜に力を入れるな ど、地域にあった品ぞろえが必要」と述べ、一層の奮起を促した。
●〜偽造事故に対処へ〜貿易証明の様式を改定 大商では本年10月1日から原産地証明書の様式を改定する。これは、昨年11月 の日商の常議員会で原産地証明書様式をはじめとする「商工会議所貿易関係証明発給 事務規則」が制定されたことに伴うもの。 以前より各地商工会議所間で原産地証明書の様式に統一性がなく、海外からその信 用性を疑問視する声があったことや、同書の偽造事故が多発していることを受け、通 産省や大蔵省の指導のもと今回の用紙改定に踏み切った。 新用紙はEU加盟国や香港、中国などで既に使用されている偽造防止加工が施され ており、大商が作成・販売するもののみ使用可能となる。新用紙は8月以降大商で販 売する。なお経過措置として、現在の様式の用紙および業者作成の私製用紙は平成12 年3月末まで使用できる。 貿易関係証明に関する新たな手引書は4月以降配布予定。大商に現在貿易関係登録 がされている企業に対しては、詳細を別途文書で連絡する。 【問合せ】国際部貿易証明担当TEL:6944−6411
●会頭コメント 『自自連立内閣成立について』 わが国の政治は果断な意思決定ができない状況にあり、これが経済の混迷に一層拍 車をかけている。自自連立内閣が強力で安定した政権となり、先の緊急経済対策など の経済再生への対応を政治主導で迅速に実行し、決断する骨太な政治に変わったとい う明確なシグナルを国内外に発信するよう期待する。 自自の政策合意のうち、政府委員の廃止、副大臣の設置、議員定数の削減は、効率 的で責任ある政治を実現するものであり、歓迎する。また、今回の組閣で閣僚数が減 ったことも、小さな政府実現の一歩として評価したい。今後とも、政策課題は両党で 速やかに協議、決定し、その過程を国民の前に明らかにしてほしい。 消費税の福祉目的税化は、社会保障制度のあり方を含めて慎重に検討する必要があ る。税金と社会保険料の国民・企業負担が重くならないよう明るいビジョンを示して、 わが国を覆う将来への不安や不信感を払拭してもらいたい。 (14日)
●資金需要衰えず〜制度の充実も寄与〜【10−12月期マルケイ】 昨年10−12月期における小企業等経営改善資金融資(マルケイ融資)の推薦実 績は、1,025件、42億1,500万円で、前年同期に比べ件数で12.0%増、 金額でも26.6%増加した。マルケイ融資への資金需要は、10月から信用保証協 会の金融安定化特別保証の取り扱いが始まったため、やや落ち着きを見せているもの の、依然として強いものがある。しかし借入金の使い道は、運転資金が全体の85% を占め、資金繰りのための資金が中心。 また新規にマルケイを推薦した企業は252件、前年同期に比べ53.7%増加し た。これは、限度額の引き上げや金利の低下などでマルケイ融資制度の充実が図られ たことや、貸し渋りの影響もあり、従来大商の支部になじみのなかった企業からの相 談が増えてきていることによる。 この結果、平成10年1年間(1−12月)の推薦実績は、件数で3,832件 (前年比28.6%増)、金額で157億6,500万円(同46.6%増)となっ た。
●「大阪企業家ミュージアム」への期待(8) 『企業家精神の神髄を学ぶ』大和銀行頭取 海保 孝 大阪商工会議所が創立120周年を記念して開設される「大阪企業家ミュージアム」 には、大きな期待を抱いている。 まず何よりも、わが国のビジネスの原点は、江戸時代には天下の台所と呼ばれ、明 治以降は大商工業都市として産業革命を担ってきた大阪にある。その大阪の輩出した 企業家の経営哲学や事績などを一堂に集めて展示紹介することの意義は誠に深い。 加えて、バーチャルの時代が進む一方で、人と人がじかに触れ合う場も大切になる。 人が集まれば、対話が生まれ、そこに叡知(えいち)と活力が湧くことにもなる。ミ ュージアムで行われる人材開発事業は、そうした時代の要請に応えるものであると思 う。 大和銀行の創業者であり、明治、大正、昭和の時代にわたる事業家であった野村徳 七もそうであるが、大阪の企業家精神については、商機を機敏につかむ才覚、時代を 先取りする進取性、信じる道を敢然と進む行動力、信用の重視、未知に挑戦する創造 性、自らの利益と顧客や社会の利益が共存するという信念といったことなどが、その 特徴としてあげられている。 自由を尊ぶ精神風土の下で、信用を重んじながら、つねに新しいものを創造してき た大阪の企業家精神を学ぶことは、これからの激動の時代においてこそ、大きな財産 となるに違いない。 そのためにも、2000年秋のオープンに向けて、今後とも万全の準備を進めてい ただければと願っている。「大阪企業家ミュージアム」が、企業家精神の神髄を広く 伝える役割を遺憾なく発揮するとともに、とりわけ次代を担う若者にとって発見の場 となり、発奮の場となることを切に期待したい。
●経営相談Q&A(55) 『輸入代理店契約書の作成』 【Q】輸入代理店契約書作成上の主な契約条項についてアドバイスしてください。 【A】取扱商品…一般に商品の名称、型式モデル番号、スペック仕様などを明記し、 品質保証の範囲と期間を設けます。輸出業者からは当該派生商品の取り扱いおよび類 似商品の開発の禁止が主張される可能性があります。 販売地域と販売権…販売地域が特定の地域のみに限定するのか、日本全域か、また 広く東アジア諸国まで含めるのか、具体的に国・地域名をあげる必要があります。さ らに販売地域における販売権にも独占あるいは非独占を明確にします。一般に輸入業 者は独占権の許諾を求めますが、独占権を得れば当然最低販売額など義務を負うこと になります。 取引条件…決済条件あるいは販売手数料とその算定基礎を明確にしておくことが大 切です。輸入価格は市況により随時変更できるようにし、価格設定の有効期限も決め ておくべきです。PL対策としては、有事の場合、輸出業者に補償できる条項を設け、 かつ賠償資力を確保するためには、PL保険契約証書のコピーを入手することを勧め ます。 期間…当初信用あるいは販売面で不安がある場合、トライアル期間を設定する方法 があります。無難な期間設定は、まず1年契約で締結し、双方異議がなければ1年ご とに自動更新するのが望ましいと思います。もし一方の当事者から条項の修正あるい は契約解除の提案があれば、期間満了の30〜60日前に文書にて通告し、相手方の 同意を得るのが一般的です。 紛争処理…クレーム処理の基準を設けておき、当事者間で紛争の解決ができないと きは、訴訟よりも仲裁による解決方法が国際取引では一般的です。この場合あらかじ め仲裁の場所、機関、規則、費用の負担まできめておき、事後問題が生じないように すべきです。 経営相談室 庁 勝TEL:6944−6471
●常議員会開く 大商は22日、第24回常議員会を開き、(1)会員加入(2)参与の委嘱の承認 (3)関西のシンボルマーク募集(4)福祉産業フォーラム・大阪99開催について 審議・了承した。 また、(1)平成10年度第34半期小企業等経営改善資金融資(マルケイ融資) 等推薦状況(2)「新入会員の集い」開催(3)野田郵政大臣との朝食懇談会開催 (4)田波大蔵事務次官との懇談会開催について報告した。 なお常議員会後の会員数は法人29,063、団体689、個人10,029の計 39,781となった。
●大型店出店 調整結果 【第二種大規模小売店舗】 ▼<店舗名>(仮称)ライフ歌島店(西淀川区歌島2−7−9)<届出者>ライフコー ポレーション<開店日>平成10年11月20日以降<店舗面積>1,200平方メー トル以下<閉店時刻>午後8時以前<年間休業日数>20日以上(10月20日大阪 府大規模小売店舗審議会にて結審) ▼<店舗名>堂島アバンザ(北区堂島1−6ほか)<届出者>ジュンク堂書店他6者 <開店日>平成11年3月1日以降<店舗面積>大型4,896平方メートル以下、 中小6者542平方メートル以下<閉店時刻>午後10時以前<年間休業日数>5日 以上(11月17日大阪府大規模小売店舗審議会にて結審)
●新時代の賃金制度探る〜雇用戦略や事例発表も〜【2月15日、大商で】 大商は、構造改革期を乗り切るための新たな賃金・雇用システムへの移行をめざし て「平成11年度賃金セミナー」を2月15日午後1時30分〜5時、大商で開催す る。 わが国経済は2年連続のマイナス成長が必至となるなど戦後最悪の状況にあり、企 業は生き残りをかけて従来の日本型経営慣行からの脱却を急いでいる。例えば賃金制 度では、個人の能力や業績を重視する成果主義賃金など新しい制度が模索されている。 雇用面では、労働者派遣法の改正など規制緩和が進み雇用形態が多様化するなかで、 生産性を高める人材活用が課題となっている。 本セミナーでは、中川逸雄・三和総合研究所組織・人事戦略開発室長が「不況期を 乗り切る賃金・雇用戦略」について、阪口克己・武田薬品工業人事組織統括室主席部 員が「成果主義賃金制度導入への取り組み」について講演する。 参加費1人6,000円(ただし『平成10年度大阪の標準者モデル賃金報告書』 持参者は1人1,000円)。 【問合せ】経済部・上野TEL:6944−6304
●チャレンジする中小企業 『品質損なわず急速冷凍、従来の固定観念破る〜共栄電熱〜』 食材を冷凍すると、本来の鮮度や風味が損なわれてしまうのは仕方ない…こんなあ きらめが食品業界にはあった。しかし「冷凍食品はおいしくない」という常識をくつ がえし、「冷凍モノでもおいしい」を実現した会社がある。西淀川区にある共栄電熱 だ。 社長の古林康男氏は、呉服屋の家に生まれたが家業が性に合わず、親しかったある 町工場の社長の下で働きながら、独学で機械や電気のことを学んだという。古林社長 が製菓・製パン業界向けの食品機械製造メーカーとして同社を創業したのが昭和40 年。その後冷凍庫の製造・販売にも乗り出すことになる。古林社長がある製パン工場 に機械を納品した折、「パン生地を冷凍保存したいが、冷気を当てると表面が乾燥し てしまう。いい方法はないものか」と相談を持ちかけられたのがきっかけ。それから 試行錯誤を繰り返し、平成2年に超急速冷凍庫「ショックフリーザー」の製品化にこ ぎつけた。 従来の冷凍方法は、食品の表面に強い冷風を当てて熱を奪うというもの。これに対 し同社は、独自の冷凍機で発生させたマイナス70度の冷気を、風速を抑えて風量だ けを大量に発生させ、なおかつ庫内を循環させない特殊な冷凍方法を採用。循環しな い冷気の中の分子だけを振動させ食品に直接伝えることで、食品表面の水分を飛ばさ ず乾燥を抑えながら急速冷凍することに成功したのだ。このため例えば焼きたてのス ポンジケーキも素早く冷凍でき、食感も失われることがないという。 またショックフリーザーでは、氷が最も大きく成長するマイナス3〜5度の温度帯 を一瞬のうちに通過させるため、通常の冷凍だと数百ミクロンに達する食品内の氷の 結晶サイズを、一ミクロン以下に抑えることができる。このため食品内の細胞が破壊 されず、解凍時に細胞内の水分や養分がドリップとして出ないことから、鮮度や風味 を保てることになる。さらに数分で食品の表面に氷の皮膜(アイスバリアー)ができ、 それがラップのような働きをするので、食品自体にも霜が付かず、冷凍焼けや乾燥を 妨げる。食品内の水分を逃さないため、庫内に霜付き現象もほとんど起こらない。鮮 魚や精肉、総菜はもちろん、炊きたてのごはんも風味を損なわずに冷凍できるように なった。 「食品の品質が落ちなければ、廃棄しなくてもよくなる。無駄をなくせるんです。 今では飲食店だけでなく、ホテル、料亭、生産ラインなどで幅広く導入してもらって います」と古林社長は言う。ショックフリーザーは、大阪市都市型産業振興センター などが主催するベンチャービジネスコンペで、昨年優秀賞を獲得した。技術の独創性 が評価されたためだ。 最近同社は、冷凍にぎりずしの『解凍庫』を開発した。通常の解凍方法だと、庫内 の温度を急速に上げるためネタまで温まってしまう。「ネタは冷たいままに、シャリ だけを温かく解凍するのが難しかった」と古林社長。現在特許を申請中だという。食 品の品質管理が厳しく問われるなかで、同社製品へのニーズは今後ますます高まるこ とになりそうだ。 (森松) <メモ>▽所在地=大阪市西淀川区福町1−5−38▽TEL:6473−2402 ▽代表=古林康男▽事業内容=製パン製菓機械、各種冷凍・解凍庫など食品機械の製 造・販売▽従業員数=14人▽資本金=1,000万円
●商店街へいらっしゃ〜い(16) 『粉浜商店街』 粉浜商店街は、南海・住吉大社駅前から線路沿いに北へ直線で400メートルほど 続く商店街。振興組合の前身である「粉浜商栄会」の発足から今年で80年を迎える。 店舗数も125店舗と大阪でも屈指の商店街だ。近くには大阪府下で一番古い住吉公 園や、人々から「すみよっさん」と親しまれている住吉大社もあり、人通りはいつも 絶えない。「商圏は半径1.5キロメートルと絞り、徹底した地元顧客志向を目指し ている」と安達久雄理事長は、同商店街がにぎわう理由をこう分析する。 そんな地元志向の商店街だが、1つだけ例外がある。商店街の名物イベントとして 定着している「はったつ市」だ。これは、住吉大社で毎月最初の「辰」の日に行われ る「初辰まいり」にちなんだもの。多くの参拝客が訪れるため、これらの参拝客を商 店街へ呼び込もうとの考えから平成2年3月にスタートした。初辰まいりと同じ日に 開催され、割引セールや福引などを実施している。「毎月、住吉大社にお参りしたあ とで、粉浜のはったつ市で買い物をする」という人が年を経るごとに増え、今では遠 方からの参拝客も楽しみにしているという。 長い歴史を持つ商店街だけに、店舗の半数近くが二代、三代と引き継がれている。 深刻な空き店舗問題もない。「後継者がいるということも一因ですが、ここの人たち は商店と住居を別々にしているので、少なくとも廃業による店舗閉鎖・空き店舗化は ありません。ここで商売をしたいという人も結構多いんですよ」と安達氏は誇らしげ だ。 近隣の商店街と連携して事業を進めているのも特徴だ。2つの商店街と1つの市場 に隣接しているが、これら四者で昭和四十八年商業協同組合を結成し、南海線の高架 下に設けた貸倉庫や駐車場を経営している。生まれた収益金は地元の夏祭りや、毎年 春に住吉公園で行われている「住吉さくらカーニバル」の運営に生かされている。 このほか、昨年から行っているアーケードの改修工事が3月に完成する。引き続き 4月からは道路のカラー舗装工事も行うという。「器の整備にメドがついた。あとは 今まで以上に、どれだけお客さんを呼び込めるかが勝負。隣接する商店街とも連携し て活性化を図っていきたい」と安達氏は強い決意を見せた。 (坂本) <メモ>粉浜商店街振興組合TEL:6671−5324、理事長=安達久雄
●【動きだす産学交流】 全国各地でTLO設立の動き技術移転は実効性が焦点に 産学交流がブームだ。象牙の塔と揶揄(やゆ)されたかつての大学のイメージとは 様変わりし、研究成果を積極的に社会に還元しようとの試みが全国各地の大学で始ま っている。米国では、80年代に大学の知的財産を活用して新産業を起こし、90年 代に入ってみごとに経済再生を果たした。不況が続く日本でも、産業界の沈滞ムード を打ち破る切り札として産学連携に期待が集まっている。 【先行する立命館大】 滋賀県草津市にある立命館大学理工学部の一角。そこにテクノコンプレックスと呼 ばれる研究施設群がある。同大学と産業界とを結び、新しい技術を生み出すための拠 点だ。立命館は企業からの委託研究や共同研究など、産学連携に早くから取り組んで いる。同大学では「リエゾンオフィス」と呼ばれる事務局が、産業界や官公庁との仲 介役を果たす。リエゾンオフィス開設当初は、理工学部教員と同オフィスの職員が、 京滋阪神地方の企業約六百社を訪問し、パイプづくりに努めたという。そのかいもあ って、受託・共同研究の実績は、オフィス開設前の94年度で30件、7,000万 円だったのが、97年度には137件、6億7,000万円と大きく伸びた。「共同 研究の中から新製品が生まれた例もあります。企業の技術力・商品開発力の向上にか なり貢献できているのでは」と同オフィスの鈴木永祐課長補佐は言う。 立命館のように研究開発面で大学と企業が連携する動きはこのところ活発化してい る。その背景には、業績低迷で研究開発費の削減を余儀なくされ、外部の頭脳である 大学を活用しようとする企業の思惑がある。しかし何よりも大きな要因は、大学が持 つ知的財産を産業界に還元し活性化を図ろうとする通産省と、社会に開かれた大学へ の改革を目指す文部省が産学連携という形で接点を見出したことだ。 【技術移転法が施行】 ここ数年、産学連携推進のための施策が相次いでいる。公務員の兼業禁止規定が緩 和され、国立大学の教員が企業に出向いて共同研究できるようになったほか、会社の プロジェクトに参加するため長期間休職しても、退職金が減額されなくなった。さら に昨年8月には「大学等技術移転促進法」が施行された。これは大学の研究成果を民 間へ技術移転する場合、その役割を担う技術移転機関(TLO)に対して、政府が資 金助成・債務保証を行ったり、特許料を免除するという内容。また技術移転を受けた 資本金1億円以上の中堅企業も、中小企業投資育成会社の出資が特例で受けられる。 同法の施行で、大学から産業界への技術移転を促すシステムがある程度整ったことに なる。 【特許の帰属問題】 研究交流が活発化すると、開発技術(特許)の帰属問題が増えてくる。特許はこれ まで個人保有が原則。従って特許出願も当然大学の教員個人が行う。しかしその作業 は煩わしく、20〜30万円もの費用がかかるため、多くの場合企業に無償で譲渡さ れていた。仮に教員が出願しても、企業相手にライセンシング活動などできない場合 が多い。そこで個人保有の特許が実用化されずに消えることになる。 しかし技術移転促進法に基づくTLOが機能すれば、こうした問題も解消する。T LOは、大学の研究者に代わって特許権を取得・維持する。一方企業には情報提供や 特許実施の許諾を行い、新商品の開発や新産業の創出に結び付けてもらう。企業から 支払われる特許使用料は研究者や大学に還元し、次の研究活動資金に活用できる。い わば『知的創造サイクル』が実現することになる。 【関西での動き】 昨年12月に、技術移転促進法に基づく4つのTLOが承認された。その中のひと つ「関西TLO」は、京都リサーチパークや立命館大、大阪中小企業投資育成、京都 大教員有志が出資して、株式会社として設立されたものだ。 同社は、関西の主要大学から多くの研究者の協力を得て、企業へ技術シーズの提供 にあたる。そのうえ出資者の京都リサーチパークや大阪中小企業投資育成とも緊密な 関係にあり、地域一体型の機関であるのが特徴。この点は、他の3つのTLOが東大、 東北大、日大という単一大学が中心の組織であるのと対象的だ。企業は年会費一口10 万円を支払って会員登録をすれば、有料ながら特許の利用や譲渡のほか、委託・共同 研究のあっせんや発明に関する情報提供が受けられる。 大きな期待がかかる関西TLOだが、取得した特許の利用料が入ってくるようにな るまでには時間がかかる。同社の中村卓爾専務は「向こう5年間は国から年間2,0 00万円の助成を受けられる見込み。その間に経営を軌道に乗せたい」と語る。 このほか関西では阪大や立命館大、関西大などでも、独自にTLOを設立しようと の動きが広がっている。今後複数のTLOが設立されることに中村専務は「将来は各 TLOがより良いシステムをめざして競争することになる」とみる。 産学の技術移転は今に始まったことではない。最近の一連の動向は、従来水面下で 行われてきた大学と企業の間の関係を表に出し、透明性を高めると同時に、大学の研 究成果の判断を市場に任せる意味を持つ。長引く不況から脱却し、景気を回復軌道に のせるためにも、大学の中で生まれた新しい技術の芽をどのように育てていくか。日 本経済の将来を左右する産学連携の実効が問われるのはこれからだ。 (森松) ◎関西TLO TEL:075−315−8250
●お知らせ ◆第40回みんなの技術教養セミナー 「バイオテクノロジーとその応用される産業分野」をテーマに、大阪市立工業研究 所の島田裕司氏が講演。1月28日午後2〜4時、大阪市中小企業指導センターで。 無料。定員100人。 ◎大阪市都市型産業振興センターTEL:6466−7701 ◆商い繁盛館「店づくり大相談会」 店舗経営者や新規開業希望者を対象に、中小企業診断士や経営コンサルタントなど が相談に応じる。(1)店舗経営=2月1〜4日午後1時30分〜5時、(2)新規 開業=1月30・31日、2月5〜7日午後1時30分〜5時、いずれも大阪南港の ATCで。定員は(1)40人(2)50人。無料。 ◎同事務局TEL:6615−5210 ◆商店経営を目指す「新規創業者養成講座〜ステップアップコース」 一定の要件を満たした受講者は、商工会議所が実施する2級販売士検定試験の一部 科目を免除。2月1日〜3月8日(全15回)午後6〜8時、大阪市商業振興企画会 議室で。無料。定員50人。 ◎大阪市商業振興企画TEL:6208−8984 ◆海外投資セミナー・融資相談室 日本企業の海外直接投資動向の現状や展望、今後有望な投資先を紹介。海外投資や 輸出入に関する融資相談も開催。2月5日午後1時30分〜4時、大商会議室で。無 料。定員70人。 ◎日本輸出入銀行大阪支店TEL:6346−4773 ◆新規事業支援、事業革新リレーセミナー 産業再活性化に向けた総合的な「事業起こし」支援を目的に開催。2月15日午後 1時30分〜5時、梅田スカイビル・タワーウエストで。無料。定員150人。 ◎近畿通商産業局TEL:6941−0997 ◆「日本でロシアを学ぶ」インテンシブコース(1) ロシア語の初心者を対象に、日常会話からロシア語でのビジネス補佐が可能なレベ ルまで集中研修を開催。サハリン州での現地研修も実施。4月12日〜7月2日、ロ シア極東国立総合大学函館校で。受講料70万円。定員10人。 ◎同校TEL:0138−26−6523 ◆「平成11年度消費者志向優良表彰」対象企業を募集 平成2年度から通産省が消費者問題に積極的に取り組み、優れた成果をあげている 企業を対象に実施しており、現在、表彰対象企業を募集しています。 ◎日本産業協会TEL:03−3501−7731 ◆平成11年度償却資産(固定資産税)の申告について 償却資産申告に際して、同申告書などのサイズ変更や申告済資産リストの送付など が実施されていますので、ご留意下さい。 ◎大阪市財政局TEL:6208−7742
●キャリアクラブ3月に講演会〜”働く女性のあり方”探る〜 大商は、大阪キャリア・クラブと共催で3月6日、『働く女性のあり方』をテーマ に特別講演会を大商国際会議ホールで開催する。 同クラブは、一流の女性企業家を数多く輩出するとともに、起業をめざす女性の資 質を向上しようと、昨年10月に発足。大商は事務局を務めるなど、全面的に活動を 支援している。 当日は、同クラブ顧問の中田幸子氏(アダマント社長)が「21世紀/キャリア・ ウーマン成功の法則」と題して基調講演を行う。続いて「輝いている『キャリア・ウ ーマン』の生き方」をテーマにシンポジウムを行う。日経ウーマンの木田昌廣編集長 やサン・インターナショナルの呉小芸社長、神戸女学院大学のキャサリン・ヴリーラ ンド教授ら第一線で活躍するパネリストが議論を繰り広げる。 参加費は一般3,500円、学生3,000円。 【問合せ】産業部・原田TEL:6944−6300
●企業家精神の発揮を〜法務講座など新企画も〜【チェンバー15号】 25日発行のチェンバー15号の特集は「今、求められる企業家精神」。 座談会では、平野茂夫・マイスターエンジニアリング社長と大西隆副会頭が、企業 の果たすべき役割や21世紀型経営のキーワードを語る。 また、不況にあっても業績好調なLSI設計のメガチップス、宿泊特化型のスーパ ーホテルの事例紹介も必見。 レイアウトが変わって、女性起業家紹介や中小企業のための法務講座など新企画も もりだくさんの15号、ぜひご覧下さい。 チェンバーは年4回発行で1部350円。会員にのみ無料配布。 【問合せ】企画広報部編集担当TEL:6944−6322
●『マルチメディアフェスティバル』〜マイドームで〜 マルチメディアコンテンツOSAKAフェスティバル実行委員会(大阪府、大阪市、 大商などで構成)は、マルチメディアコンテンツ市場の育成を図るため、「マルチメ ディアコンテンツOSAKAフェスティバル’99」を2月2〜4日、マイドームお おさかで開催する。 ホームページやCD−ROMなどの展示会のほか、マルチメディアビジネス活用に 関する商談会、プレゼンテーション、セミナー、グランプリなどを実施する。 【問合せ】同フェスティバル事務局(コングレ内)TEL:6360−6577
●週40時間労働制全事業場で適用【労働省】 平成9年4月1日から一部を除き、すべての事業場で週40時間労働制が適用され ています。また、導入にあたり、2年間の行政指導期間が設けられていましたが、今 年3月31日で終了します。 週40時間労働制の導入を進め、従業員にゆとりとやる気、職場の活気を生み出し ましょう。
●【大商あっせん】ドック検診 大商では各検診機関と提携し、成人病や脳の検診を実施しています。 お忙しい方でも短時間にほぼ全身のチェックができる人間ドック。 MR(磁気共鳴診断装置)の開発で、脳卒中などのチェックができる脳ドック。毎 年1回早期発見、早期治療のために受診されてはいかがでしょうか。 【問合せ】会員サービス課TEL:6944−6253
●大商セミナー ▼以下の問い合わせは企業研修部 研修 担当TEL:944−6422へ。 【新入社員対象講座】 ○新入社員基礎講座 (社会人としての基礎知識を学ぶ) 時期=4月2日、受講料=12,500円、定員=500人 ○新入社員接遇応対講座 (実習やロールプレイング中心に、来客接遇・電話応対などを学ぶ) A:時期=4月5日(1日集中)、受講料=24,000円、定員=60人 B:時期=4月6・7日(2日間集中)、受講料=36,000円、定員=60人 ○ビジネス実務入門講座 (会社の仕組みや仕事への取り組み方、ビジネス文書作成などを学ぶ) 時期=4月8日、受講料=24,000円、定員=80人 ○ビジネスマナー入門講座 (若手社員対象に、心構えやマナー、効率的な仕事の進め方を学ぶ) 時期=4月9日、受講料=24,000円、定員=80人 ○新入社員合宿訓練講座 (ビジネスマナー、規律、職場でのチームワークなどを体得する) A:時期=4月12〜14日、受講料=62,000円、定員=60人 B:時期=4月15〜17日、受講料=62,000円、定員=60人 ○営業社員基礎講座 (好印象のセールストークや営業テクニックを学ぶ) 時期=4月20日、受講料=24,000円、定員=80人 ○ビジネス電話応対講座 (電話対応の基礎からクレーム処理までを実習) A:時期=4月22日(午前)、受講料=15,000円、定員=35人 B:時期=4月22日(午後)、受講料=15,000円、定員=35人 ○パソコン速習講座 (1人1台体制でWindows98、Word97、 Excel97の基本操作を習得) A:時期=4月9・10日、受講料=28,000円、定員=18人 B:時期=4月13・14日、受講料=28,000円、定員=18人 C:時期=4月15・16日、受講料=28,000円、定員=18人 【大商パソコンカレッジ】 ○パソコン入門2日間講座 開催日=2月16・18日、3月17・18日 受講料=会員24,000円/人(税込)、一般36,000円/人(税込)。 ○インターネットと電子メール入門講座(1日間) 開催日=1月27日、2月23日 受講料=会員12,000円/人(税込)、一般18,000円/人(税込)。 ○パソコン土日完習講座〜2人に1人が付き指導〜 開催日=2月20・21日 受講料=会員40,000円/人(税込)、一般60,000円/人(税込)。 (注)定員=各18人、土日講座10人、時間=各日とも10〜17時 会場=エールカレントカレッジ(難波駅近く) 【中小企業情報化実践講座】 情報化の実践ノウハウを解説し、具体的な成功・失敗事例を紹介。2月2日午前1 0時〜午後4時30分、大商会議室で。講師は市村経営事務所所長の市村保雄氏。受 講料=会員24,000円、一般36,000円。定員60人。 【目標管理制度導入講座】 経営幹部を対象に、自社の目標達成と社員の士気向上につながる「目標管理制度」 の運営方法や目標設定の仕方、指導方法を解説。2月4日午前10時〜午後5時、大 商会議室で。講師は人材活性化研究所代表の内海滋夫氏。受講料=会員24,000 円、一般36,000円。定員60人。 【改正法人税と中小企業の優遇税制セミナー】 2月9日午前10時〜午後5時、大商会議室で。講師は日経システムズ社長の山崎 修一氏。受講料=会員24,000円、一般36,000円。定員70人。 【経営者大学】 「経営のコツ〜本当の経済・本物の経営」と題して船井総合研究所会長の船井幸雄 氏が講演。さらに同研究所大阪経営指導本部長の高島栄氏がコンサルティング現場か らみた企業の生き残り策について、成功企業の事例を挙げながら提言するほか、国際 金融アナリストの増田俊男氏が株価や為替、景気の動向を分析。2月15日午後1時 30分〜5時30分、大商国際会議ホールで。参加費=会員15,000円、一般 18,000円。 【営業社員のための与信管理実践講座】 取引先の信用調査から日々のチェックポイント、倒産時の対応、債権の保全・回収 までをケーススタディを中心に分かりやすく解説し、与信管理能力向上を図る。2月 16日午前10時〜午後5時、大商会議室で。講師は与信管理実務コンサルタントの 武藤豊氏。受講料=会員24,000円、一般36,000円。定員80人。 【人事労務管理の戦略的な見直し講座】 4月施行の改正労働基準法の中身を正しく理解し、効率的な組織運営や生産性向上 に結びつく新時代の人事労務管理のあり方を学ぶ。2月23日午前10時〜午後5時、 大商会議室で。講師は賃金管理研究所の宮下馨氏。受講料=会員24,000円、一 般36,000円。定員60人。 【営業マン道場】 若手営業マンを対象に、合宿を通じて必須の知識やセールステクニックをロールプ レイングを通じて習得し、真の戦力に鍛え上げる。3月11〜13日、養福寺会館 (京都市左京区)で。講師は実践教育研究所所長の三浦操氏。受講料=会員70,0 00円、一般105,000円。定員30人。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 【新規開業支援セミナー】 「創造・起業〜経営管理の留意点」をテーマに、グローバル監査法人の多田幸生氏 による講演のほか、マルケイ融資「新規開業者経営改善貸付制度」の解説も行う。2 月12日午後1時30分〜3時、大商会議室で。無料。定員150人。申込締切日2 月5日。 ◎中小企業相談所経営相談室TEL:6944−6471 【ビジネス中国語講座】 法律や時事、ビジネス関連用語を用いた文書の日本語への翻訳や中国語での文書作 成などを行う。中国語(普通語)中級以上の方対象。2月15日〜3月18日(全1 0回)時間は各日とも午後6時15分〜8時、大商会議室で。講師は日中経済協会関 西本部参与の藤本恒氏。受講料=会員30,000円、一般40,000円。定員2 5人。 ◎国際部・梁TEL:6944−6400 【ビジネス英会話講座】 仕事で英語を使う機会のある方を対象に、グループワークによる英会話やリスニン グ訓練を中心に、国際ビジネスでの心構えなどを学ぶ。2月19日〜3月16日(全 7回)午後6時30分〜8時、大商会議室で。講師は大阪外国語大学助教授の高橋伸 光氏。受講料=会員28,000円、一般35,000円。定員50人。 ◎国際部・辻TEL:6944−6412
●支部セミナー ◆中小企業における社員にやる気を起こさせる賃金制度導入セミナー 東成支部主催。業種・業態に合った「動機付け賃金制度」の導入を考える。2月1・ 4・8日(全3回)いずれも午後6時30分〜8時30分、同支部で。講師は実践人 事代表取締役の山口和夫氏。受講料6,000円。定員20人。TEL:6974− 4121 ◆知っておきたい税務知識 都島支部主催。(1)税改正を考える(2)パソコンなどの活用。2月9日午後6 時〜7時30分、同支部で。講師は経営指導員の狭間和男。受講料1,000円。定 員30人。TEL:6924−3351 ◆Windows95/98の基礎講座 生野支部主催。パソコン初心者を対象に開催。2月9・12日(全2回)午後6〜 8時、同支部で。講師はエヌ・エヌ・エー・テンダーサービスの佐藤元相氏。受講料 4,000円。定員10人。TEL:6754−1025 ◆国際化時代のキーワード・ISO9000シリーズ 東成支部主催。同シリーズの認証について、事例を交えて体系的に説明。2月9日 午後6時〜7時30分、同支部で。講師は日本品質保証機構ISO関西支部の福井博 氏。無料。定員30人。TEL:6974−4121 ◆コンピューター西暦2000年問題 東成支部主催。最終リミットの迫った同問題の問題点と対応策について専門家が解 説。2月10日午後6時〜7時30分、同支部で。講師はSCC関西支店のシステム エンジニアリング・マネージャー。無料。定員30人。TEL:6974−4121 ◆活用パソコン入門セミナー〜基本操作からインターネットまで 大正支部主催。Windows・Word・Excelの操作やインターネット、 Eメールについて、基本と活用のコースに分けパソコン1人1台体制で実施。<基本> 2月10〜24日(全5回)、<活用>3月3〜17日(全5回)いずれも午後2〜 4時、NTT新町営業所で。受講料5,000円。定員15人。TEL:6553− 8110 ◆経営改善セミナー〜ネットワーク時代の経営戦略と経営システム 生野支部主催。2月18日午後5時30分〜8時30分、生野産業会館で。講師は 経営指導員で中小企業診断士の古賀隆幸。無料。定員20人。TEL:6754−1 025
●めざそう!オンリーワン都市(30) 『試される「集客都市」大阪』 歴史街道推進協議会 事務局長 井戸智樹
●時代を拓く〜永年会員企業訪問〜(4) 文:安達 史典 『ペット関連事業も第2の柱に』
●どう取り組む?環境(8) 『ISO14001認証審査のポイント』 監査法人トーマツ 主任コンサルタント 小野木 正人
●商店のかんどころ(7) 『スタンプ活用したイベント−販促シリーズ(2)−』 田阪経営研究所 代表 田阪 薫

[大阪商工会議所のトップページへ戻る]
Copyright(C)1999 大阪商工会議所




